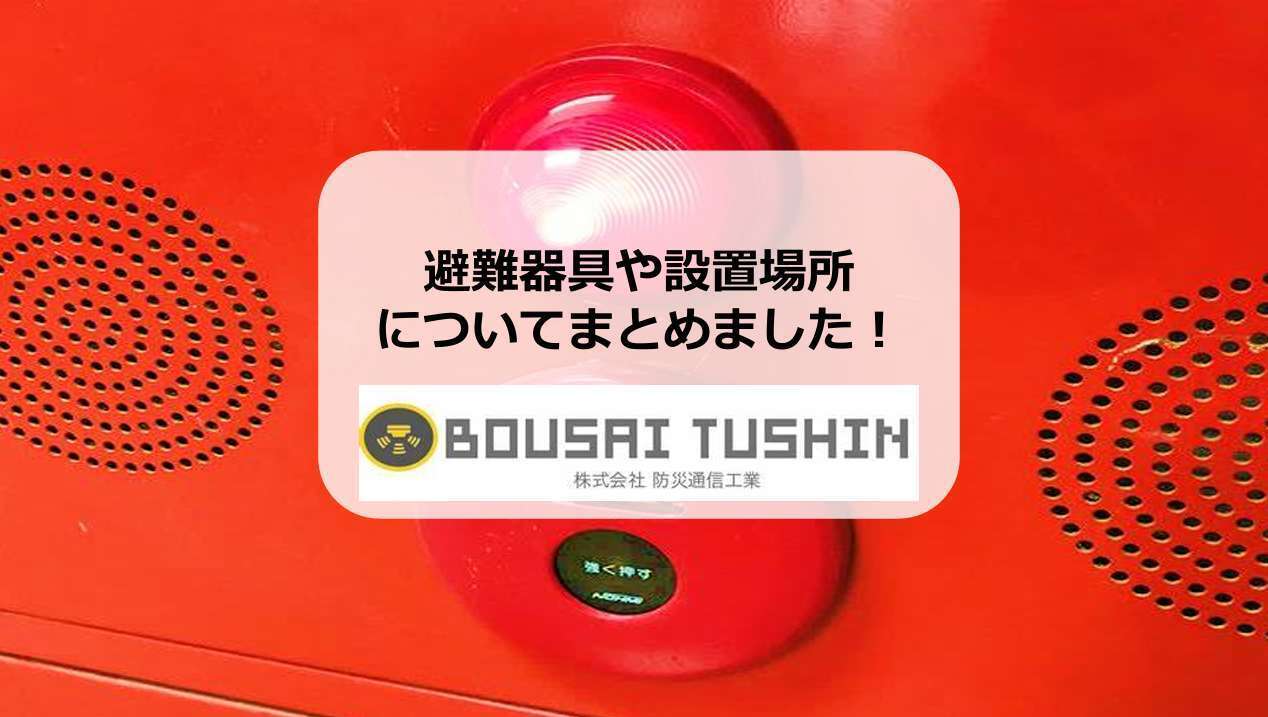千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
本日は避難器具について詳しくご紹介したいと思います。
この記事を読んでわかること
・避難器具(避難はしご・緩降機・救助袋・滑り台・避難用タラップ・避難橋・避難ロープ・すべり棒)
・避難器具の設置が求められる場所
・日常点検について

避難器具とは
避難器具とは、火災や地震などの緊急時に避難するための専用の器具を指します。通常、避難は階段や廊下といった避難経路を利用しますが、これらが使用できない場合に備えて設置されているのが避難器具です。具体的には、ベランダや屋上に備え付けられた「はしご」や「ロープ」、「救助袋」などが挙げられます。
これらの器具は、煙や火の影響で避難階段や通路が使えない場合や、逃げ遅れた際に使用されるものです。そのため、避難器具はすべての人が利用するものではなく、通常の避難経路が利用できない非常時に限定される「非常用の器具」としての役割を持っています。
避難器具
避難器具には主に8つの種類があります。
避難はしご
「避難はしご」は、縦棒や横桟、突子などで構成されたはしごを指します。素材は金属製のものと、樹脂など金属以外の素材で作られたものがあります。形状や使用方法によって以下のタイプに分類されます。
・固定はしご
・立てかけはしご
・吊り下げはしご
・ハッチ格納式吊り下げはしご
これらは、設置場所や用途に応じて使い分けられます。
緩降機(かんこうき)
自分の体重を利用してゆっくりと降下し、安全に避難階へ移動するための器具です。かつては一人用と多人数用が存在しましたが、現在ではほとんど一人用が使用されています。
この器具は、ロープの先端に取り付けられた「着用具」を体に装着し、降下中に「調速器」を使用して速度を調整します。降下速度は16~150㎝/秒の範囲で設定でき、平均的には80~100㎝/秒で安定した降下が可能です。
ただし、ロープ一本に体重を預ける構造のため、使用にはある程度の勇気が必要とされます。
救助袋
垂直式と斜降式の2種類があり、学校のベランダなどに設置されることが多い装置です。
垂直式は、垂直に広がる袋の中をらせん状に滑り降りて避難する仕組みです。
一方、斜降式は布製の滑降面を大きな滑り台のように展開し、その上を滑りながら避難します。
滑り台
その名の通り滑り台のような形状で、公園などによくある滑り台を大きくしたようなものです。
滑り台には直線型とらせん型の2種類があり、避難器具の中では比較的簡単に避難できる反面、設置費用が最も高いとされています。
主に幼稚園や老人ホームなどの社会福祉施設に設置されており、介助が必要な方でも安全に避難できるのが大きな特徴です。
避難用タラップ
階段状のタラップを普段は収納しておき、使用時に展開して利用する仕組みです。
ちなみに「タラップ」という言葉はオランダ語が由来であり、船や飛行機の乗り降りのために一時的に架設される構造物という意味があります。
避難橋
建物同士をつなぐ橋のことで、使用時に避難橋を押し出して隣の建物まで架けて避難します。ただし、これを設置するには「建物同士の高さが同じであること」や「建物間で合意があること」などの条件が必要なため、あまり普及していません。
避難ロープ
ロープの上端を建物や固定具に取り付け、垂らしたロープを使って降下する、非常にシンプルな避難器具です。
コストは低いものの、設置できる場所が限られ、また2階からの避難にしか利用できない点が特徴です。
すべり棒
学校の遊具にある「のぼり棒」を逆にしたようなもので、垂直に固定された棒をつかみながら滑り降りる器具です。
避難器具の設置が求められる場所
これまでに紹介してきた消防用設備は、主に防火対象物の用途や延べ面積によって設置の必要性が決定されていました。一方、避難器具については、建物の用途や該当階の収容人数、さらに避難階段(特別避難階段)の有無などが基準となるため、判断が複雑です。
例えば、消防法施工令別表第一の7項(学校など)の場合、建物の主要構造部が耐火構造であれば2階に避難器具の設置は不要です。3階以上の階では、階ごとの収容人数に応じて設置が必要で、50~200人なら1つ、201~400人なら2つの避難器具を設置する必要があります(特別避難階段の減免を考慮しない場合)。また、設置できる器具の種類も用途や階によって異なります。この例でいうと、3階には滑り棒と避難ロープ以外の器具であれば設置可能です。
日常点検について
避難器具の日常点検は、比較的簡単に確認できる項目が多いため、以下のポイントを意識して点検を行いましょう。
・適切な位置に設置されているか
・避難器具に簡単に近づけるか
・器具のある部屋が施錠されていないか(ただし、サムターン錠は除く)
・使用時に邪魔になる物が周囲にないか
・展開や使用に必要なスペース(操作面積)が確保されているか
・標識と器具が離れた場所に設置されていないか
・標識が脱落したり、見えにくくなっていないか(不鮮明ではないか)
これらを目視で確認して、安全性を確保してください。
避難器具の設置場所の適正性
避難はしごや緩降機など、窓枠や専用の固定具に取り付けて使用する器具は、設置場所に邪魔な物がないか、模様替えなどで固定具が取り外されていないかを目視で確認します。
降下空間や避難空地の適正性
避難はしごや救助袋など、降下させて使用する器具については、降下部分に樹木や電線などの障害物がないか、また着地場所に邪魔な物や樹木がないかを目視で確認します。
器具本体の状態
避難はしごやロープ、緩降機などの器具本体に、変形・破損・さびがないかを確認します。また、格納箱に収納されている器具は適切に収納されているか、格納箱自体がさびて穴が開くなどの劣化がないかも目視で確認します。
避難通路や階段の適正性
避難器具は避難階段や避難廊下が使用できない場合の補助手段として設置されています。そのため、避難の際にはまず避難階段や廊下が優先されます。
これらの通路や階段に避難の妨げとなる物が置かれていないか、つまずきや滑りの原因がないか、容易に進入できる状態か、さらに階段や手すりが変形・破損・さびていないかを目視で確認します。
まとめ
避難器具は避難階段や避難廊下が適切に確保されていることでその効果を発揮します。そのため、避難器具の点検だけでなく、避難階段や避難廊下に物品を置かないことも非常に重要です。特に、避難階段の出入口に設置されている防火シャッターや防火戸の周辺(いわゆるくぐり戸の部分)にも物を置かないように十分注意しましょう。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!